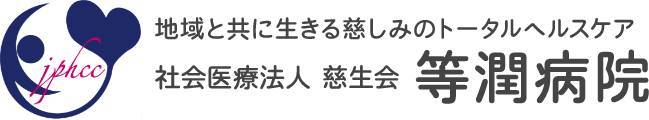診療技術部 検査科
ご紹介
臨床検査とは採取された血液や尿等の検査を行う「検体検査」と、心電図や肺活量等身体の状態を直接検査する「生理機能検査」があります。
私たち臨床検査技師は医師の指示のもとに、病気の診断や治療方針を決めるのに必要な情報を得るため、各種検査を行っています。
患者様に安心して検査を受けていただけるよう、また正確かつ質の高い情報を迅速に提供していけるよう日々技術の向上に努めています。
検体検査
- 生化学検査(肝機能、腎機能、電解質、糖尿病検査)
- 血液学検査(血算、血液像、凝固系)
- 一般検査(尿定量、尿沈渣、便潜血検査、髄液検査)
- 各種迅速検査(インフルエンザ、アデノウイルス、ロタウイルス、RSウイルス、ノロウイルス、溶連菌、肺炎球菌、マイコプラズマ、レジオネラ、心筋トロポニンT、妊娠反応…等)
- 免疫学検査(感染症、腫瘍マーカー)
- 輸血検査
- 細菌検査
- 病理検査

生理検査
心電図検査
心臓が動くときに発生する微弱な電流を体表面から記録したものが心電図です。
ベッドに仰向けに寝た状態で両手両足首と胸部に電極を取り付け波形の記録を行います。不整脈や心筋障害、心肥大等を調べることが出来ます。
他に24時間心電図を記録できるホルター心電図、運動中の胸痛や不整脈等を調べるための負荷心電図(マスター法、トレッドミル法)等も行っています。

血圧脈波検査(ABI/PWV)
両腕・両足首の4カ所で同時に血圧を測定し、血管の硬さ(動脈硬化)や血管の狭窄・閉塞を評価することが出来ます。 動脈硬化を早期に発見し動脈硬化と関連のある病気の予防に役立てるために有効であると言われています。
呼吸機能検査
検査技師の掛け声に合わせて息を吸ったり吐いたりして検査を行い、 肺の容積や空気を出し入れする換気機能のレベルを調べることができる検査です。
COPDや肺気腫等の肺の病気を評価することができます。 麻酔を使用する手術の前にも肺の機能を確認するために検査を行うことがあります。

超音波検査
超音波検査は人の耳には聞こえない周波数の高い音波(超音波)を体内に当て、 その反射した超音波を画像化することにより、 各臓器の形状や血管内を流れる血液の速さ等を調べるものです。
超音波は無侵襲的で安全な検査なので頻回に検査をすることができ、 長時間にわたる精密検査や病気の進行度合いを比較する場合にも用いられます。
当院では腹部(肝臓、胆嚢、腎臓、脾臓、膵臓、膀胱)、心臓、頸動脈、下肢血管、乳腺、甲状腺等の領域を検査しています。

脳波検査
脳波とは、脳が活動するときに発生する微弱な電流を頭皮上から記録したものです。
検査は頭に電極を装着し、ベッドに横になって目を閉じたリラックスした状態で行い、 光刺激や過呼吸(早い呼吸)等の負荷刺激を加えた記録も行っていきます。
失神等の意識障害がある場合やてんかん・脳炎等脳に関する病気を調べるための検査です。
神経伝導速度検査
誘発筋電図検査とは筋または神経を電流で刺激し、それによって誘発された筋や神経の活動電位を記録する検査です。
検査中装置を当てているところがピリピリ感、痛み、違和感を憶えるかもしれませんが、体には害はないので心配いりません。
運動障害(動き難さ、脱力)、知覚障害(感覚の鈍さ、しびれ、痛み等)の原因が筋によるものなのか神経によるものなのか、またその障害部位や障害の程度を調べるための検査です。
尿流量測定ウロフロメトリー検査
トイレ型の便器におしっこをするだけで排尿の勢いを数値化し、 排尿パタ-ンを客観的に確認することができます。
前立腺肥大症等排尿障害を調べる検査です。

睡眠時無呼吸検査
睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは、その名の通り睡眠時に呼吸が止まるまたは浅く弱くなり、それが原因で日常生活に様々な障害を引き起こす疾患です。
一般的にSASの重症度はAHI(Apnea Hypopnea Index)=無呼吸低呼吸指数で表すことが多く、 これは一晩の睡眠を通して1時間あたりの無呼吸・低呼吸の発生する回数を意味します。
このAHIが5回以上認められ、日中の眠気等の自覚症状がある場合にSASと診断されます。
睡眠時無呼吸症候群を代表とする睡眠呼吸障害の検査方法としては、 簡易睡眠呼吸検査装置等によるスクリーニング検査と、 睡眠障害の有無を含めた精密な検査である終夜睡眠ポリグラフィ(PSG)があり、 当院ではどちらの検査も受けていただくことが可能です。